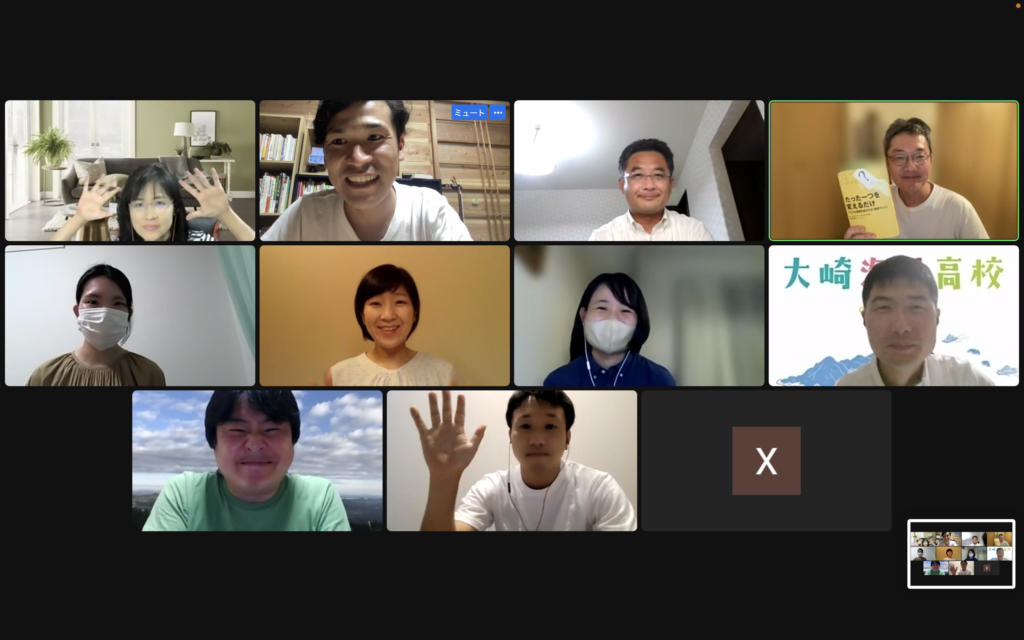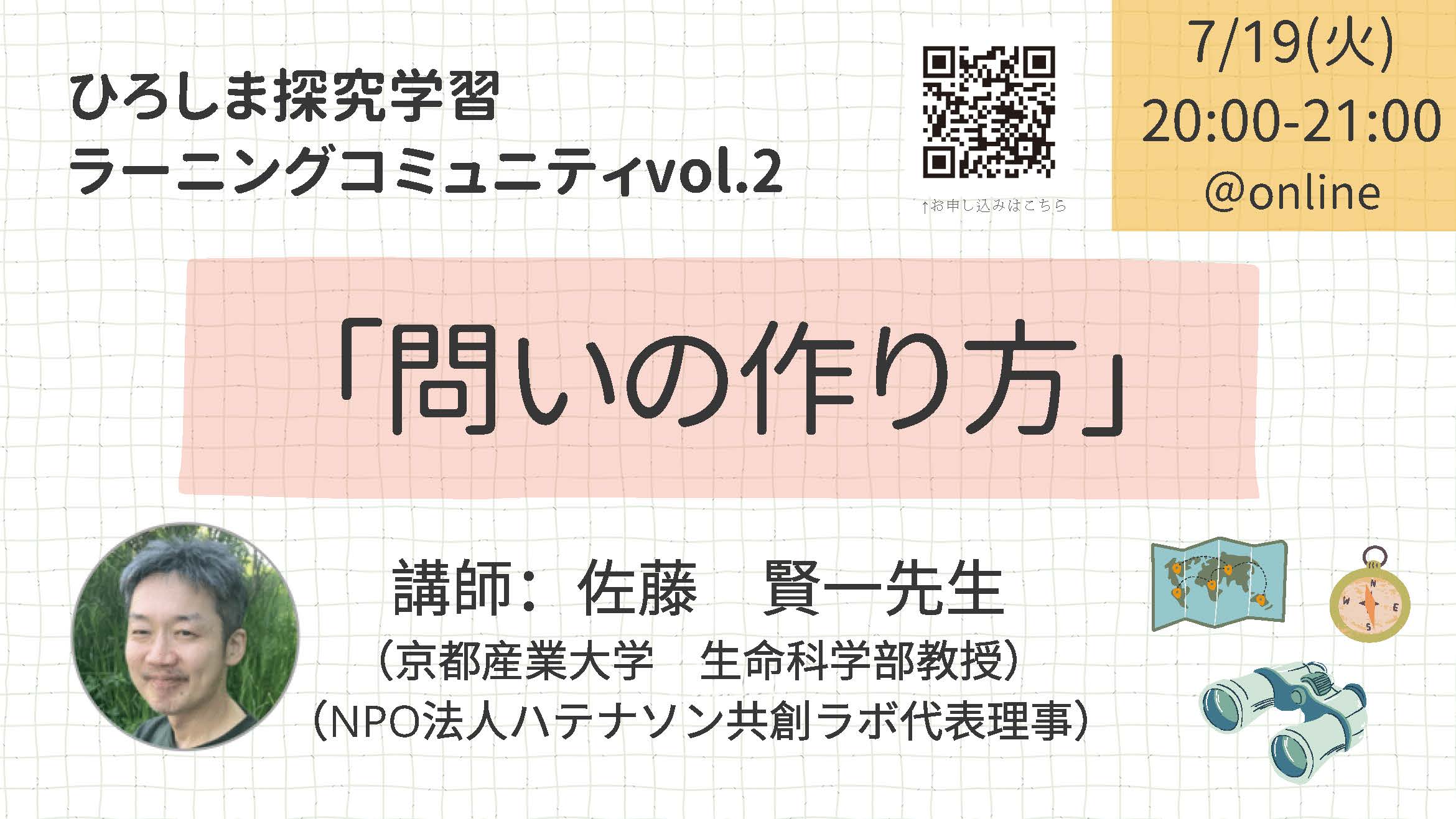広島県内で、探究学習に関心のある先生・コーディネーター達で学び合う「ひろしま探究学習ラーニングコミュニティ」
今回は、NPO法人ハテナソン共創ラボ代表理事の佐藤賢一先生を講師にお招きし、「問いの作り方」をテーマに勉強会を行いました。
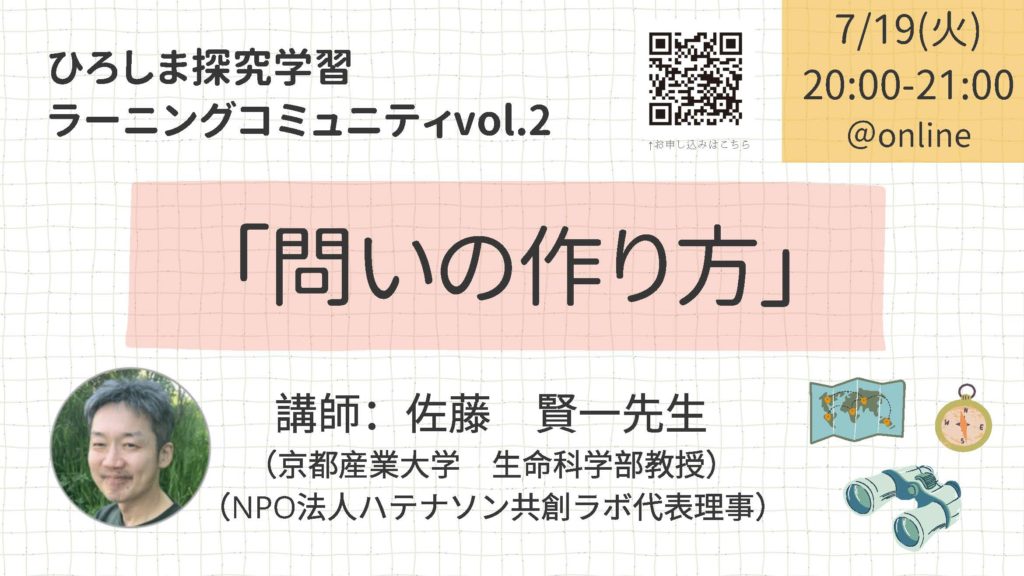
授業の中で「問い」を出しているのは誰だろう?
佐藤先生は、京都産業大学の教授として、生命科学を研究されています。
ある時、『たった一つを変えるだけークラスも教師も自立する「質問づくり」ー』 という一冊の本との出会い、感銘を受けたことから、NPO法人を立ち上げられて、学習者が質問づくりを行うメソッドの研究・普及に努められてきました。
最初に佐藤先生から「このグラフは何のグラフでしょうか?」という問いが投げかけられます。そこには2本の棒グラフがあります。実は、これはある授業中に、教師と生徒のどちらが多くの質問を発しているか、を表したデータ。圧倒的に、教師が発する質問のデータの割合が大きい・・・。
また、もう一つ、別のグラフを提示いただきます。そこに示されたのは、子どもたちの書く力や読む力、質問する力が、年齢と共にどのように変化していくかを示したグラフ。書く力、読む力は、年齢を追うごとに伸びているのに対して、質問する力は、歳を追うごとに、減退していく様子が示されます。
授業の中に「問いづくり」を取り入れるには?
どうすれば、学習者の質問する力を育んでいけるのでしょうか?
佐藤先生に大きな影響を与えた本の『たった一つを変えるだけ』というタイトル。さて、ここで言う「たった一つの変えるもの」とは、一体何でしょうか。実は「質問する人を、教師から学習者に変える」という点なんです。
お話を聞きながら、実際のワークをシュミレーションし、学習者が質問づくりを行なっていく授業のプロセスを学んでいきます。
印象的だったワークは、「問い重ね」と「問いの変換」です。一つの問いに対して、さらに問いを投げかけて、一つの問いから、沢山の問いが出すのが「問い重ね」です。また、一つの問いを、オープンクエッションに変えたり、クローズドクエッションに変えたり、変換していくのが「問いの変換」です。
これらを繰り返していくと、一つの問いから、沢山の問いを出すことができ、また、何を問いたいのかというポイントが明確になっていきます。そして優先順位を考えていく。自分が問いたいことを明らかにしていくのが、質問づくりのワークでした。
参加者の感想を、ご紹介します。
・ウォーミングアップとしての『問いあつめ』なども行いながら『問いづくり』をもとにした授業づくりを行ってみようと思いました。
・『問い』を出し合うためのプロセスを学ぶことができてよかったです。また,出し合った問いをどのように活かしていくかという事もしっかりと考えながら教科でも『問い』をつくる授業を行えたらと思います。
・「いい質問だね」「鋭い!」はなんとなく言うのに抵抗があったのですが、この言葉は逆に全体を抑圧してしまうという説明を聞いて、目からウロコが落ちました。今後気をつけていきたいと思います。
・良い問い•悪い問いというものはない。それぞれの問いが「活きる場面」があるだけ、と言うことを学びました。
まとめ
問いづくりは、決して難しいことではなく、ウォーミングアップのような形でも良いので、少しずつでも、授業の中に取り入れられることが分かりました。実践してみよう、と声が会の終了時に溢れていました。
実は勉強会が終わった後の、放課後タイムで、佐藤先生からこんな言葉を伺いました。
「どんな問いに対しても感謝の言葉を」
子どもの出してくれた一つ一つの問いに、「ありがとう」という気持ちを持つことが、問いが沢山出てくるクラスづくりのポイントだそう。実践していきたい、大切な姿勢だと感じました。